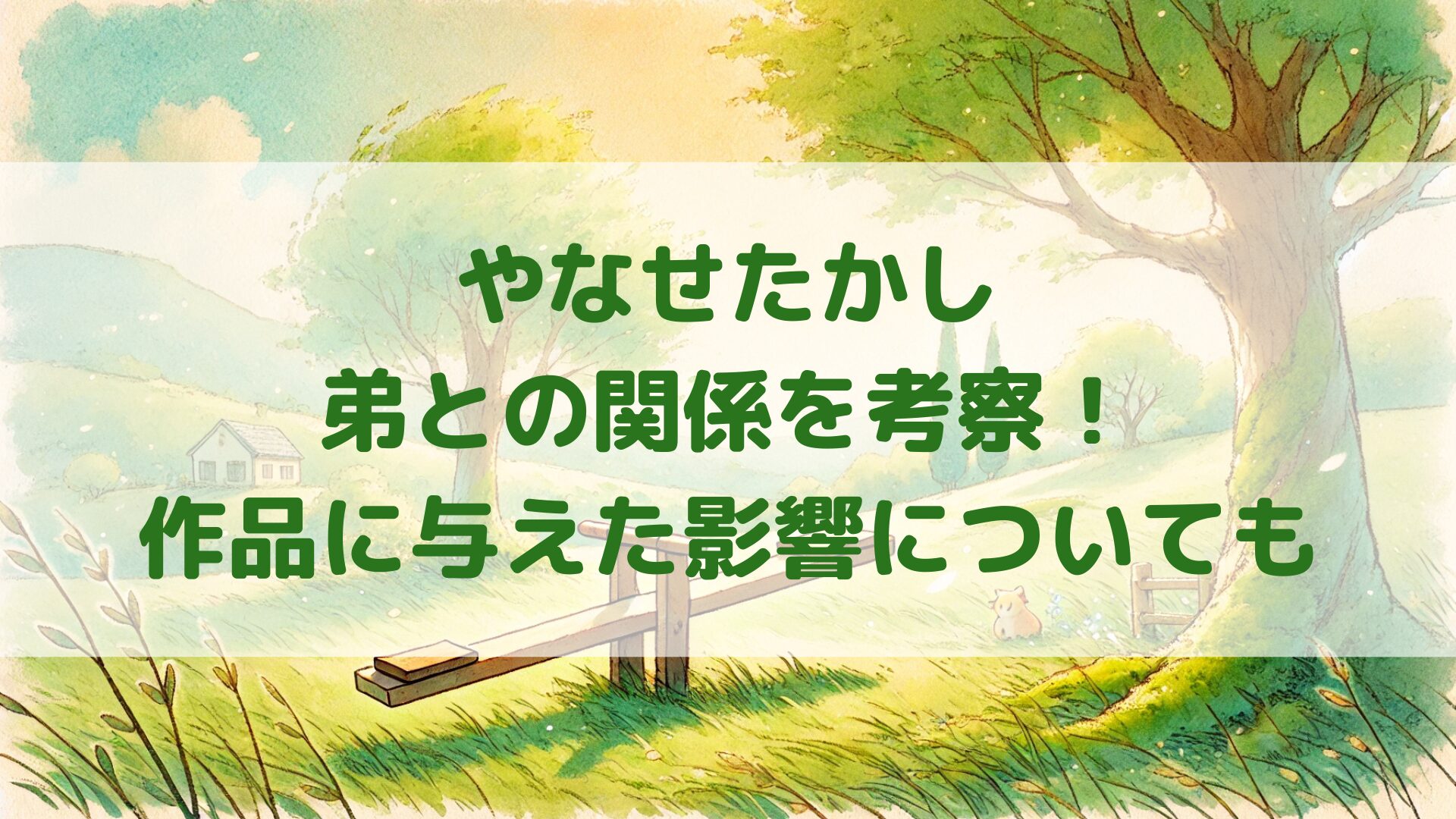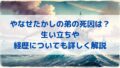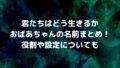アンパンマンの生みの親として知られるやなせたかし。
その温かい作品の背景には、戦争で失った弟・千尋との関係が深く影響しています。
やなせたかしの中で、弟・千尋の存在は特別なものでした。
今回はやなせたかしと弟・千尋との関係を考察し、弟の死が彼の作品にどのような影響を与えたのかを詳しく紹介します。
やなせたかしと弟の関係を考察!
🏃♀️#あんぱんだより🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) March 25, 2025
本日放送した「#知恵泉」は #NHKプラス にて見逃し配信中👀https://t.co/J6DGI39ygG
※配信期限:4/1(火) 午後10:44まで
苦難の連続だったという #やなせたかし さんの人生。
ぜひチェックしてみてください👀#中沢元紀#朝ドラあんぱん
📅3月31日(月)スタート🏃
やなせと弟は一度離れ離れになりますが、また一緒に暮らすことに。
それでは、二人の関係について始めます。
やなせたかしは弟とは違い一種の疎外感を感じていた
弟・千尋は長岡郡後免町(現・南国市)で開業医を営んでいた伯父・寛に引き取られ、やがて養子縁組しました。
母親が再婚したため、やなせも弟のいる伯父の元に預けられましたが、養子縁組はしていません。
伯父夫妻は両方の子供を大切にしてくれましたが、やなせは一種の疎外感を感じていたようです。
既に養子縁組をしていた千尋は、すっかり伯父の家での生活になじんでいました。
伯父夫妻はやなせのことも、とても大切にしてくれたようですが、どこか疎外感を感じていたのでしょう。
やなせは香北町朴ノ木地区にあった父の実家に通い、井伏鱒二や太宰治らの本を読みあさっていたそうです。
自分の居場所を探し、実家の本の世界に逃避していたのではないでしょうか。
複雑な兄弟関係「シーソー」
🏃♀️#きょうのあんぱん🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) April 1, 2025
物心ついた時から絵を描くことが好きだった嵩🎨
嵩の絵をみた伯父・寛は
「嵩、こじゃんと絵を描け」
「好きなものはやればやるばあ、こじゃんと好きになる」
🔻背中を押してもらえた嵩の表情に注目👀https://t.co/P3AYQGScxT#木村優来 #竹野内豊#朝ドラあんぱん pic.twitter.com/S3sqFYTfHA
やなせと千尋の関係は、やなせの詩集『おとうとものがたり』に詳しく描かれています。
その中に「シーソーというかなしい遊びがある」という詩があります。
小さい頃の千尋は病気がちで学校の成績も良くなく、一方のやなせは健康で成績も良かった。
千尋は薬を飲みながらお菓子や玩具に囲まれ、やなせは嫉妬から病気になりたくて雨にびしょぬれになったりしたそうです。
しかし中学生になると状況は逆転し、千尋は頑丈になり柔道2段の優等生に、やなせは柔道無段の劣等生になりました。
やなせはこの関係を「一方が上がれば一方が下がる」シーソーに例え、「それでもぼくらは仲良しだった」と振り返っています。
この詩は、兄弟間の複雑な感情や競争関係を象徴しており、やなせが千尋に対して抱いていた複雑な思いが伝わってきます。
伯父の家で養子として暮らす千尋と、預けられただけのやなせという立場の違いが、こうした心境の違いにも影響していたかもしれません。
▼シーソーの詩は【やなせたかしおとうとものがたり】で読むことが出来ます
やなせは弟の分まで生きた
官立旧制東京高等工芸学校図案科を卒業後、やなせは東京田辺製薬の宣伝部に就職。
しかし1941年に徴兵され、陸軍に入隊しました。一方の千尋は京都帝国大学に進学し、その後海軍に志願。
千尋は海軍中尉として1944年12月30日、フィリピン沖のバシー海峡で乗船していた駆逐艦「呉竹」が敵の攻撃を受け沈没。
享年22歳でこの世を去りました。
やなせは「弟の千尋は特殊潜航艇の乗組員としてフィリピン沖バシー海峡の海底に沈み、遺骨も何もなく、骨壺の中には海軍中尉柳瀬千尋と書いた木札が一枚だけだった」と語っています。
「ぼくは泣かなかった。まったく見えないところで弟は消えてしまった。名前のように、弟は千尋の深海に沈んだ」というやなせの言葉には、突然弟を失った悲しみと、その喪失感を受け入れられない気持ちが表れています。
戦争から生還したやなせは「弟の分まで生きる」という思いを胸に、戦後の漫画家人生を歩み始めることになります。
やなせたかしの作品に弟が与えた影響
弟・千尋の死はやなせたかしに大きな喪失感をもたらしました。
戦争を体験し、弟を失ったやなせの心には深い悲しみと共に、平和への強い希求が芽生えました。
この体験は彼の創作活動に色濃く反映され、後の作品の根底にある「弱者への眼差し」や「他者を思いやる心」などの価値観形成に大きな影響を与えたのです。
ここからは、やなせたかしの作品に弟が与えた影響について始めます。
『おとうとものがたり』に込められた思い
やなせは弟への思いを詩集『おとうとものがたり』に綴りました。
この作品は「弟よ、君の青春はいったい何だったのだろう」という問いかけから始まり、やなせの内に秘めた深い感情が静かに浮かび上がる内容となっています。
戦争に翻弄され、短い生涯を終えた弟への追悼の気持ちが色濃く反映されたのが、この詩集です。
二度と弟と遊ぶことができないという喪失感と、それでも心の中で弟と共に歩み続けるという決意を感じさせる詩もあります。
この詩集はやなせにとって、弟との思い出を形にし、その死を受け入れるための重要な作業だったのかもしれません。
巻末エッセイには、弟の死を通して彼が得た人生観が綴られています。
弟の短い生涯を見つめることで、やなせは「生きる意味」や「他者のために自分を犠牲にする勇気」について深く考えるようになったのでしょう。
こうした思索が、後のアンパンマンのような自己犠牲の精神を持ったキャラクター創造につながっていったのではないでしょうか。
▼やなせたかしのうちに秘めた思いが綴られています
『手のひらを太陽に』と生きることの尊さ
戦後、漫画家としての道を歩み始めたやなせでしたが、仕事に恵まれない時期もありました。
ある冬の寒い日、落ち込んでいたやなせは電気スタンドの灯りで手を温め、その血管が透けて見える様子から「悲しいのも苦しいのもつらいのも生きているからだ」と気づきます。
この体験から生まれた詩「手のひらを太陽に」は、作曲家のいずみたくが曲をつけ、1969年には小学6年生の教科書に採用されました。
この曲には、弟の分も生きるという強い思いが込められています。
やなせたかし自身、この詩が生まれた背景について「弟の分まで生きなければ」という思いがあったと語っています。
弟を失った悲しみを抱えながらも、それを乗り越えて前向きに生きようとする姿勢が、この詩には表れています。
アンパンマンに込められた弟への思い
やなせの代表作「アンパンマン」にも、戦争体験と弟への思いが投影されています。
「アンパンマンマーチ」の歌詞に込められた問いかけには、難しすぎると批判する声もありましたが、やなせはこれを大切にしました。
これは若くして命を落とした弟の人生に対する問いかけでもあったのでしょう。
また「アンパンマンマーチ」には、戦場で命を落とした人々への思いが込められているという見方も。
アンパンマンが自分の顔を分け与えて空腹の子どもを助ける設定には、「戦争中に一番堪えられなかったのは飢え」というやなせ自身の体験が反映されています。
1969年に初めて世に出た『アンパンマン』は、マントを翻して空を飛び、飢えた子どもにあんぱんを配る太ったおじさんで、敵の戦闘機と間違えられて撃ち落とされるという悲しい結末でした。
自分の顔を食べさせることについて「残酷だ」という批判に対し、やなせは「正義の味方が最初にやらないといけないのはひもじい人を助けること」「正義を行う人は自分が傷つくことを覚悟しなきゃいけないんだ」と主張し続けました。
この信念の背景には、弟を含む戦争犠牲者への思いがあったのかもしれません。
まとめ
今回はやなせたかしと弟・千尋との関係を考察し、弟の死が彼の作品にどのような影響を与えたのかを詳しく紹介しました。
やなせたかしと弟・千尋の関係は、幼少期「シーソー」のような複雑なものでした。
養子縁組した千尋と異なり、やなせは伯父の家で預かってもらうという立場の違いから、幼い頃は疎外感を抱いていたことも考えられます。
しかし戦争で弟を失った悲しみは、やなせの創作活動に大きな影響を与えました。
『おとうとものがたり』に綴られた弟への思い、『手のひらを太陽に』に込められた生きることの尊さ、そしてアンパンマンが体現する「他者を思いやる心」には、すべて弟・千尋の存在が深く関わっています。
「弟の分も生きる」という強い思いを胸に、やなせたかしは数々の名作を生み出しました。
その作品に込められたメッセージは、平和の尊さや命の大切さを訴え、今も多くの人々の心に届いています。
弟の短い人生と、その死が深く刻まれたやなせの作品は、これからも多くの子どもたちに夢と希望を与え続けることでしょう。
それこそが、やなせたかしが弟・千尋の分まで生き抜いた証なのかもしれません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。